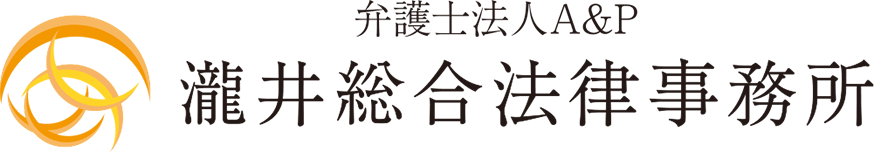子供の発達段階に応じた面会交流の工夫
2025/6/16
子供は、成長の過程で心身ともに大きく変化していきます。
そのため、子供にとって適切な面会交流を実施するには、子供の年齢や発達段階に応じて、面会交流の方法や頻度等について、柔軟に対応することが求められます。
今回は、年齢段階ごとの特徴に即した面会交流の工夫や注意点について解説します。
2 学童期(6~12歳)の面会交流
3 思春期(13歳〜)の面会交流
4 長期休暇中の面会交流:夏休み・冬休みの活用方法
5 まとめ:子供の成長に合わせた柔軟な対応の重要性
6 よくある疑問とその回答(FAQ)
1 乳幼児期(0歳~5歳)の面会交流
子供は親に養育される中で、生後5、6か月で親と他者の区別が可能となり、自分の知らない者に対して警戒感を示し、人見知りをするようになる、といわれています。そのため、別居により一緒にいる時間が短い別居親に対して、子供が人見知りをすることもよく見られます。
しかし、人見知りをするといっても、この頃の子供は人に対する興味があること、一緒に過ごす時間を積み重ねることで親として認識し得ることからも、適切な親子関係を形成するため、乳児期から面会交流を実施することは重要です。
もっとも、乳児期の子供は特に、同居親から離れることで不安を覚えやすく、加えて子供の身の回りの世話のためが必須であることから、同居親の付き添いが必要な場面も多いといえます。
そのため、双方が対面で会うことを避けることが望ましいケース(たとえばDV事案など)を除き、通常のケースでは、同居親の立会いを要する場面は多いのが現状です。もっとも、乳児期=立会いが必要というものではなく、面会交流中に子供の身の回りの世話はどのように行うのか具体的に考え、子供に過度の負担を与えない面会交流の方法を検討する必要があります。
乳幼児の場合、朝から晩までといった長時間の面会交流ではなく、数時間の面会交流が適切な場面が多く見受けられます。別居親が別居前に主に子供を監護していた場合には、長時間や宿泊付きの面会交流実施を検討してみてもよいでしょう。
2 学童期(6~12歳)の面会交流
学童期は、学校生活や友人関係、習い事などで生活リズムが安定してきます。面会交流も、子供の予定や気持ちに寄り添いながら柔軟に設計することがポイントです。親の都合でスケジュールを押しつけるのではなく、子供の日常生活に支障をきたさないよう、同居親や子供と相談しながら進める姿勢が重要です。
月1回土日のどちらかに会うという方法ももちろんありますが、必ずしも定期的な面会交流にこだわる必要はありません。子供が習い事やスポーツクラブに加入している場合は、送迎を担当、練習の見守り、試合への帯同等、子供と一緒に過ごす時間を確保することも可能です。子供の日常生活に合わせ、生活のペースを乱さないことが継続的な面会交流の実施につながります。
小学校高学年となると、さらに習い事や友達付き合いのため忙しくなる子供も多くいます。そのため、子供の年齢に合わせて、時間だけでなく、会う回数や面会場所、面会時に何を行うのか(遊び、食事等)を柔軟に変更する必要があります。
3 思春期(13歳〜)の面会交流
思春期は、子供が自立に向けて親との距離感を探る時期です。この時期の面会交流では、子供の気持ちや意思を尊重し、無理強いせずに信頼関係を築くことが重要です。
子供によっては、面会そのものに消極的になったり、気分の波によって態度が変わることもあります。しかし、そうした反応を否定せず、「会うこと」よりも「関わりを持ち続けること」に重きを置いた姿勢が大切です。
LINEやメッセージアプリ、SNSなどを通じて、日常的なやり取りを続けることで、自然な形でつながりを保つこともできます。特にこの時期は、子供のプライバシーや世界観を尊重する姿勢が、面会交流の継続につながります。
子供との時間が沈黙になっても、焦らずに一緒にいること自体を大切にし、否定せずに受け止める態度が、長期的な信頼関係の基盤になります。
4 長期休暇中の面会交流:夏休み・冬休みの活用方法
普段は学校や習い事で時間が取りづらい場合でも、夏休みや冬休みは、面会交流を拡大する絶好の機会となります。旅行やイベント、特別な体験を通じて、日常とは異なる形での交流ができ、親子の絆をより深めることができます。
計画段階から子供の希望を聞き、無理のないスケジュールを立てることが重要です。他の家族との予定や塾・部活動のスケジュールなどにも配慮し、子供が面会を負担に感じないような工夫が求められます。
また、旅行などの場合は、安全性や宿泊先の環境、緊急時の連絡体制について、事前に十分な確認を行っておくことが必要です。
5 まとめ:子供の成長に合わせた柔軟な対応の重要性
面会交流は、親の希望を押しつける場ではなく、子供が安心して別居親と関係を築くための大切な機会です。年齢や発達段階ごとに、子供のニーズは大きく変化します。その変化に寄り添いながら、柔軟で無理のない交流方法を工夫することが、継続的な関係の維持につながります。
別居親としては、「どうすれば子供が安心して会えるか」「何を大切にしているか」に意識を向けながら、押しつけず、誠実に向き合う姿勢が求められます。面会交流は、子供にとってかけがえのない親子関係を築くための、大切な時間といえます。
6 よくある疑問とその回答(FAQ)
Q:面会交流は乳児でも行うべきですか?
A:はい。乳児期でも短時間・立ち会い付きで行えば親子関係の構築に有益です。無理のない頻度と方法を検討しましょう。
Q:面会交流の頻度に決まりはありますか?
A:法律で明確な頻度は定められていません。子供の年齢や生活環境に合わせて柔軟に調整することが大切です。
Q:子供が面会を嫌がる場合はどうすれば?
A:無理に会わせるのではなく、子供の気持ちを尊重しつつ、LINE等でつながりを保つなど代替手段も検討しましょう。
当事務所では、こうした面会交流に関するご不安やお悩みに丁寧に寄り添い、適切なアドバイスを心がけています。お気軽にご相談ください。
▽そのほか、離婚に関する記事をお読みになりたい方はこちらから。
離婚関連記事