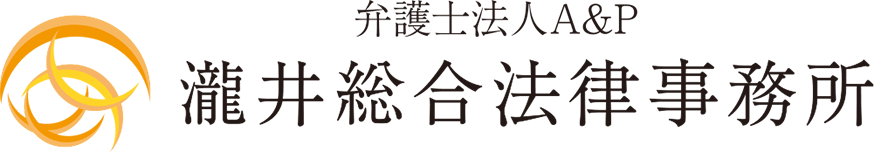養育費未払いに対する強制執行について補助制度が始まります
2025/4/10
2025年4月より、大阪市で新たに養育費の強制執行に係る着手金補助制度が開始されます。この制度を利用することで、養育費を支払わない親に対して法的手続きを取る際の費用負担を軽減することが可能となります。
すでに豊中市や吹田市などでも養育費の強制執行に関する補助制度が開始されています。これらの市でも、養育費の未払いを解決するための法的手続きを進めやすくするため、ひとり親家庭の負担軽減を目指したサポートが行われています。
以下では、養育費未払いに対する強制執行の方法、弁護士の必要性を説明した上で、補助の内容について解説します。
1 養育費未払いに対して強制執行を行う方法
養育費未払いに対して、相手に催促をしても相手が任意に支払いをしない場合、給与や預貯金、不動産などを差し押さえるために、強制執行手続きを執ることとなります。
強制執行とは、裁判所の手続きを通じて相手方の財産を差し押さえ、未払い養育費を回収する方法です。強制執行を行うためには、「債務名義」を取得して、強制執行の申立てを行うという二段階の手続が必要です。
(1)養育費未払いに対する強制執行に必要な「債務名義」
強制執行を申し立てるには、「債務名義」というものが必要になります(民事執行法22条)。養育費未払いに関する強制執行で代表的なのは、以下のものです。
① 強制執行認諾文言が記載された公正証書(民事執行法22条5号)
離婚前または離婚後に、養育費について、支払う金額や支払う時期、期間を明記して、未払いが生じた場合に強制執行を可能とする旨の文言が記載された公正証書を指します。
公証役場において、公証人に作成をしてもらうものが公正証書です。
一般的には、案文を公証人に伝え、公正証書作成日を決めた上で、公証役場に双方が赴いて作成することになります。このときに、弁護士に依頼をしていれば、弁護士が代理人として代わりに出向いて作成することも可能です。
② 調停調書、審判、判決(民事執行法1号、3号、7号)
家庭裁判所において、養育費の支払いについて調停が成立した場合、裁判所の審判によって養育費の支払いが命じられた場合、離婚が判決によって命じられた場合に養育費の支払いも命じられている場合、などは家庭裁判所が作成した調停調書、審判、判決が債務名義となります。
(2)強制執行の申立て
債務名義が取得できれば、差し押さえる対象財産を特定して、強制執行を申し立てることとなります。
通常、差押えは申立て時の未払い分のみについてのみ可能なのが原則です(民事執行法30条1項)。しかし、養育費については、養育費の一部が未払いの場合、将来分についても差し押さえることが可能です。なお、養育費未払い分の差押えは、相手の有する財産のどれでも対象とすることができますが、養育費将来分を差し押さえる場合は、給与など毎月相手に支払われる債権となります(民事執行法151条の2)。
給与を差し押さえる場合、養育費についてはさらなる特例があります。通常、毎月の給与に対する差押えは、手取り額の4分の3(ただし、33万円まで)は差し押さえることができません。しかし、養育費の場合は、これが手取り額の2分の1までとされています(民事執行法152条3項)。
このように、養育費の場合は、差し押さえる範囲や金額において、他の場合と比較して保護が手厚くなっています。
2 弁護士に依頼する必要性
上記でも述べたとおり、強制執行には、債務名義の取得と強制執行の申立てという二段階の手続が必要です。
既に債務名義がある場合は、強制執行の申立てだけで済みますが、どの財産を差し押さえるのが効果的か、また、そもそも財産が分からず調査が必要、というときには、弁護士の専門的知見が役に立ちます。弁護士が必要な場面は、大きく次の場面です。
(1)債務名義の取得
債務名義がそもそもない場合、まずは債務名義の取得が必要です。弁護士の目線からは、離婚前に養育費を取り決めた上で、債務名義まで作っておくというのがベストになります。そのため、離婚前の時点から弁護士の関与がある方が、いざというときには手続が少なくて済む可能性が高いです。
養育費を取り決めることなく離婚した場合であっても、離婚後に養育費を取り決めることは可能です。離婚した相手方と直接連絡を取りたくない場合や、養育費の金額の妥当性が分からない場合は、弁護士の知見が役に立ちます。
(2)財産の調査
相手の財産が分からない場合、民事執行法に基づく財産の調査や、弁護士会照会を利用した調査などにより、相手方の財産を突き止められる場合があります。
特に、民事執行法に基づく財産の調査は、養育費については市町村や日本年金機構などに対する調査が認められているのが特色です(民事執行法206条)。これにより、相手の勤務先を特定できる可能性があり、給与の差押えに役立ちます。
(3)差押え対象財産の選定
差し押さえるべき財産をどれにするのかも、強制執行においては大切なポイントです。
養育費の場合は、基本的には給与の差押えが第一選択となりますが、未払いが多額に及んでいる場合は、他の財産に対する差押えも検討が必要です。
差押え対象財産の選定によっては、調査から差押えまで一気通貫で通すべき場面がありますので、弁護士に依頼いただくことを検討した方がよいといえます。
3 大阪市の補助の内容
大阪市では、ひとり親家庭に対する金銭的支援として、これまでも、公正証書等作成時の公証人手数料、調停等の裁判所に申立てを行う際の印紙等について、補助を行ってきました。2025年4月からは、これに加えて、弁護士費用の補助制度も開始されます。補助の内容は以下の通りです。
<対象者>: 養育費の支払いが確定した調停証書、公正証書、確定判決等の債務名義を持つひとり親(その他、収入要件等があります。)
<補助額>: 補助金の上限は15万円(予定)
<実施時期>: 2025年4月(予定)
冒頭でも触れた通り、既に大阪府内の複数の市町村では、弁護士費用の補助が行われています。
相手が養育費を支払う能力があるのに支払わない場合、これらの制度の活用によって養育費の未払いが解消されることが望まれます。
4 まとめ
大阪市の新たな補助制度は、養育費の未払いに悩むひとり親家庭を支援する重要な制度です。この制度を活用することで、強制執行の費用負担を減らし、養育費を確実に回収できる可能性が高まります。
弊所では、養育費の回収に関するご相談はもちろんのこと、養育費の額等を定めていない場合のご相談も受け付けております。お困りの際はぜひ一度ご相談ください。
執筆者:弁護士 稲生 貴子
▽そのほか、離婚に関する記事をお読みになりたい方はこちらから。
離婚関連記事