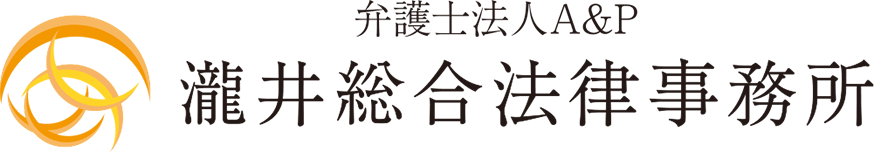カスハラガイドライン
2025/2/18
近年、顧客からの過度な要求や暴言、威圧的な言動など、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が社会問題となっています。これに対し、厚生労働省は企業が適切に対応できるよう「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(以下「カスハラマニュアル」といいます。)を作成しました。本記事では、カスハラマニュアルの内容について紹介しつつ、企業や従業員がカスハラにどう対処すべきかを解説します。
2 カスハラマニュアルの目的と背景~カスハラ対策が義務化へ~
3 カスハラ対策
(1)カスハラを想定した事前の準備
(2)カスハラが実際に起こった場合の対応
4 おわりに
なお、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」については以下のリンクからダウンロードすることができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
1 カスタマーハラスメントとは
カスタマーハラスメントとは、カスハラマニュアルによると、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義されています(カスハラマニュアルp7)。
具体的には、企業が提供する商品・サービスに欠陥が認められないにもかかわらず、商品の交換や金銭の補償を要求する行為や、長時間にわたるクレームの押し付け、人格を否定するような発言、業務外の対応を強要する行為などが該当します。
「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」や、「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」があるか否かがポイントとなります。
2 カスハラマニュアルの目的と背景~カスハラ対策が義務化へ~
厚生労働省が作成した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」は、企業がカスハラに適切に対応し、従業員の安全と健康を守るための指針を提供することを目的としています。近年、カスハラによる従業員の労働災害やメンタルヘルスの問題が増加しています。また、企業にとっても、カスハラにより経済的損失やブランドイメージの低下などが生じる可能性があり、カスハラ対策が急務となっています。
令和6年12月16日、厚生労働省は、全ての企業に対し、カスハラから従業員を保護する対策を義務付ける方針を示し、令和7年の通常国会で関連法案の提出を目指すことになりました。
このように、カスハラ対策は今後企業の義務となっていくことになります。そのため、企業としてはカスハラマニュアルを参考にしながら、カスハラ対策を講じていくことが求められます。
3 カスハラ対策
カスハラマニュアル18ページ以下では、企業が具体的に取り組むべきカスハラ対策が掲載されています。
以下ではカスハラ対策の基本的な枠組みを紹介します。
(1)カスハラを想定した事前の準備
① 基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発
カスハラに対する企業の基本的な方針や姿勢を明確にし、従業員に周知します。企業として、基本方針や姿勢を明確にすることにより、企業が従業員を守り、尊重しながら業務を進めるという安心感が従業員に育まれます。
② 従業員のための相談対応体制の整備
カスハラを受けた場合に従業員が気軽に相談できるように、相談対応者や相談窓口を設置します。
③ 対応方法、手順の策定
カスハラを受けた場合の対応方法については、予め準備しておくことが肝要です。
カスハラには様々な態様がありますが、いくつかのパターンに分類することが可能なはずです。そこで、企業ごとにカスハラのパターンを事前に想定し、対応方法、手順について準備しておくことで、スムーズな対応が可能になります。
④ 社内対応ルールの従業員等への教育・研修
カスハラの対応方法、手順を策定したら、実際にカスハラを受けた場合に対応できるように、従業員への教育・研修を行います。過去に現場で発生した事案や経験等を踏まえた事例の紹介やケーススタディを設けると、よりよい教育・研修効果が期待できます。
(2)カスハラが実際に起こった場合の対応
① 事実関係の正確な確認と事案への対応
実際に顧客からクレーム等があった場合、それが正当な主張なのか、カスハラに当たるものなのか、確かな証拠・証言を基に事実関係を確認します。
② 従業員への配慮の措置
従業員がカスハラを受けた場合、速やかに従業員の安全を確保する措置を採る必要があります。また、メンタルヘルスの不調が認められる場合は、産業医や臨床心理士等の専門家に対応を依頼するなどのアフターケアも重要です。
③ 再発防止のための取り組み
カスハラ問題が一旦解決した後は、再発防止に向けた取り組みをすることになります。今後も同様の事象が起きないためにも、社内で問題点や解決策の共有や、勉強会を行う、マニュアルの見直しなどの再発防止策が考えられます。
4 おわりに
本記事では、カスハラガイドラインについての概要を説明しました。詳細は、厚生労働省作成の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を確認していただきたいのですが、実際に各企業に応じたカスハラ対策マニュアルを作成するのは容易ではありません。
カスハラは、態様によっては警察や弁護士など外部機関との連携や法的な対応が必要となるケースが多いので、法律の専門家である弁護士を交えてマニュアルを作成することが望ましいです。
各企業に応じたマニュアルの作成のためにも、弁護士に相談されることをお勧めします。
監修者 弁護士 森本 禎
▽カスタマーハラスメントに関する記事をお読みになりたい方はこちらから。
カスハラとは?定義やリスク・クレームの違いについて解説!
▽そのほか、事業に関する記事をお読みになりたい方はこちらから。
事業関連コラム