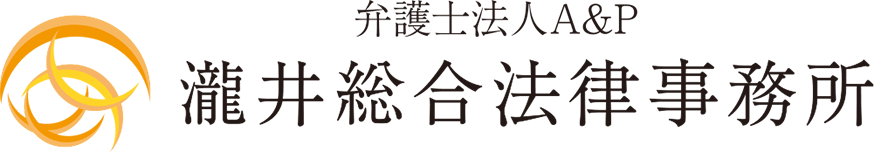事務局便りvol.79(法律事務職の部屋vol.4~裁判管轄~)
2025/2/18
みなさま、こんにちは。事務局のnです。
本日の事務局だよりは『法律事務職の部屋vol.4裁判管轄』です。
「裁判管轄」とは、嚙み砕いて言うと、どの事件をどの裁判所に提起(申立)するべきか、というお話です。
さて、全国に裁判所はいくつあるでしょうか。
答えは、最高裁判所1+高等裁判所14+地方裁判所253+簡易裁判所438+家庭裁判所770(出張所を含む)=合計1,036庁です。
そんなにあるの!?と感じた方もいらっしゃったのではないでしょうか。
これほど多くの裁判所のうち、「どの事件をどの裁判所に提起(申立)するべきか」を定めているのが裁判管轄であり、民事事件(金銭の貸し借りに代表される私人間の紛争)については民事訴訟法に、家事事件(離婚・相続に代表される家庭内の紛争)については、家事事件手続法にその規定があります。
さっそく条文を覗いてみましょう。
民事訴訟法第4条(普通裁判籍による管轄)
1 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
民事訴訟法ですから、民事事件についての規定ですね。
民事事件の場合は、(第一義的には)被告の住所地を管轄する裁判所へ訴えを提起しなければなりません。
なお訴訟では、訴えを提起した当事者を「原告」、訴えを提起された当事者を「被告」と言います。
ですから、あなたが訴訟を提起しようとするときには、あなたの住所地ではなく、相手方の住所地を管轄する裁判所へ訴えを提起しなければならない、ということになります。
しかし、これはあくまでも原則であり、例外となる規定も複数存在します。
その一例を挙げます。
民事訴訟法第5条(財産権上の訴え等についての管轄)
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
(略)
9 不法行為に関する訴え 不法行為があった地
(略)
不法行為の代表的なものは交通事故です。ですから、交通事故により被った損害を請求する訴訟の場合は、交通事故が発生した場所を管轄する裁判所へも訴訟が提起できるということになります。
その他、当事者同士でどこの裁判所に係属させるかを決めることもできます。
民事訴訟法第11条(管轄の合意)
1 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
契約書の最後には、定型句のように「本契約に基づく紛争については、〇〇裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」といった表現が見られますが、これは第11条の規定に基づくものです。
他にも例外規定はありますので、A裁判所・B裁判所・C裁判所のいずれにも訴えを提起することができるというケースもあり得ます。
その場合は、原告が裁判管轄を有する裁判所の中から任意に選択し、訴えを提起してよいので、弁護士は訴訟を進めるにあたり少しでも有利な裁判所を選択することになります。
コロナ渦以降、民事訴訟法の改正もあり、オンラインの方法による裁判期日の実施が普及してきましたが、尋問や和解など、まだまだ裁判所への出頭を要することがあるからです。
弁護士から訴状の提出の指示があったとき、事務員が真っ先に確認すべき事項がこの「裁判管轄」です。
移送(裁判所が他の裁判所へ事件を移すことを言います。)という制度もありますが、多くの場合、裁判管轄のない裁判所では訴状を受理してもらえませんので、その分時間と手間をロスすることになるからです。
弁護士も人間、間違うことはあり得ます。ダブルチェックという意味でも、事務員にとって裁判管轄に関する知識は必須なのです。
法律事務の実務に踏み込んだ内容でしたが、いかがでしたでしょうか。
次回のテーマは「とある一日のスケジュール」を予定しています。お楽しみに。
▽そのほか、事務局便りをお読みになりたい方はこちらから。
事務局便り関連記事