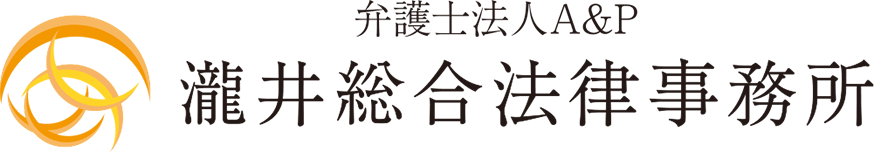ネット誹謗中傷対応
2023/5/31現代社会においては、インターネット上で誰でも自由に表現活動や情報発信ができるようになりました。
その反面、誰しもが名誉を毀損されたり、プライバシーを暴露されたり、悪評を流されたりするなどの誹謗中傷を受けるリスクが起こり得るようになりました。
特に、有名人であったり、会社を経営していたりすると、誹謗中傷を受けるリスクは高くなりますし、それが拡散すると今後の活動や会社の業績などに深刻な影響を受けることになります。
そこで、今回はネットで誹謗中傷を受けた際の対応についてご紹介します。
1誹謗中傷を受けないためには~言動に注意~
誹謗中傷は、ご自身に全く非の無いケースでも起こり得るものですが、そのようなケースは別として、そもそもなるべく誹謗中傷を受けないように振る舞うことが重要です。
特に、犯罪などの違法行為に関する事実関係を暴露された場合は、名誉やプライバシーを侵害するものであっても、公益性があるとして違法とは認められず、削除や損害賠償請求などの措置が採れなくなる可能性があるので、日ごろの言動に注意しましょう。
2誹謗中傷を受けたら~①削除請求~
ネット上で誹謗中傷を受けた場合の対応として、削除請求があります。
削除の方法は大きく分けて、⑴各サイトの削除フォームやメールなどからサイトの運営者に削除を依頼する方法と、⑵裁判手続きによる削除請求があります。
⑴削除フォームなどからの削除依頼
削除フォームなどからの削除依頼は、費用をかけることなく簡単にすることができます。
また、依頼後は即時~数日で削除に応じる場合があり、迅速に削除が完了することもあります。
もっとも、サイトによっては何の対応もされないこともありますし、削除を拒否されることもあります。
⑵裁判手続きによる削除請求
各サイトが任意に削除しない場合は、裁判所に削除の仮処分の申し立てをすることになります。
裁判所において削除が相当であると認定されると、多くのサイトでは削除に応じてくれます。
もっとも、裁判所で削除が相当か慎重に判断されるので、削除フォームによる削除よりも時間がかかります。
また、裁判手続きはご自身で行うのは難易度が高いので、弁護士に依頼する方が良いですが相応の費用が掛かります(海外のサイトを相手にする場合は、申立書等の翻訳にかかる費用も必要になることがあります。)。
3誹謗中傷を受けたら~②発信者情報開示請求と損害賠償請求~
削除請求は、ネット上にある誹謗中傷の投稿を取り除く、いわば守りの対応です。
削除請求だけでは誹謗中傷をした相手方を知ることはできません。
攻めの対応として、誹謗中傷した相手方を特定のために発信者情報開示請求という手続を行い、損害賠償請求を行うことも可能です。
⑴発信者情報開示請求
発信者情報開示請求は裁判手続きでなくとも行えますが、実際はプロバイダが裁判手続きを経ずに任意に応じることはほとんど無いので、基本的には裁判所に対して発信者情報開示請求を申立てます。
裁判手続きによる削除請求同様、ご自身で行うのは難易度が高いので、弁護士に依頼する方が良いですが相応の費用が掛かります。
発信者情報開示請求は、サイト管理者やプロバイダの保存する通信ログ等の開示を求めますが、通信ログの保存期間は3か月から6か月程度なので、投稿後迅速に開示請求を行わないと開示を受けることができなくなってしまうため注意が必要です。
⑵損害賠償請求
発信者情報開示請求により、誹謗中傷をした相手方が特定できたら、損害賠償請求をすることができます。
賠償額の相場は、誹謗中傷の内容によって違ってきますが、一般的には、個人の場合は10~50万円、法人の場合は50~100万円程度になります。
獲得できる賠償額は想像していたよりも低額と思われるかもしれません。
しかし、単に誹謗中傷を削除するだけでは、新たに投稿がなされれば根本的な解決にはなりません。
そのため、相手方を特定し、損害賠償請求を行うことは、二度と誹謗中傷をしないように釘を刺すという効果が期待できます。
4誹謗中傷を受けたら~③刑事告訴~
上記は民事での対応になりますが、誹謗中傷のうち、侮辱や名誉毀損に当たる場合は犯罪になる可能性があるので、刑事告訴をすることも可能です。
5誹謗中傷を受けたら~④その他の対応~
その他の方法としては、削除をするのではなく、法人であれば自社のホームページに反論文を掲載するという方法もあります。
また、削除が困難な場合は、逆SEO対策をしてなるべく検索上位に上がって来ないようにする方法も有益でしょう。
被害があまり大きくない場合に、積極的に削除等の対策をすることで、かえって炎上が大きくなる可能性があります。
そのような場合は、あえて何もしないという対応をすることも選択肢の一つです。
6誹謗中傷を受けたときは弁護士に相談を
以上のように、ネットで誹謗中傷を受けた際の対応についてご紹介しました。
ネットの書き込みは、ネガティブな内容であればどのようなものでも削除等が認められるわけではありません。
また、誹謗中傷の投稿を放っておくと拡散し、削除や投稿者の特定も困難になりますので、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
弊所では、ネット記事削除の案件も取り扱っておりますので、下記リンクもご参照ください。