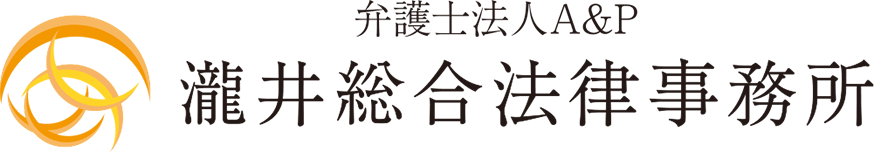今更聞けない?相続の基本な流れ~相続手続の手順やしなければならないことについて~
2021/7/9こんにちは。
今回は、相続に関する基本的な流れを説明いたします。
一言で「相続」といっても、なにをどうする手続きであるかは、当事者になった方でないと分からないかもしれません。
いつか、自分の身に起こってしまうであろう相続について、基本的な流れをご説明いたします。
1死亡届の提出
死亡届とは人が亡くなったときに提出が義務付けられている書類です。
故人の死を知ってから7日以内に、故人の本籍地か死亡地、または、届出人の居住地にある役所で提出できます。
死亡届を出すと「埋火葬許可証」をもらえます。
これがないと、火葬も埋葬も行えません。
万が一、許可なしで火葬をした場合には、1000円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処するとされています(墓地、埋葬等に関する法律第21、22条)し、火葬許可証がない場合、基本的には火葬場が火葬を受け付けてくれません。
また、死亡届には医師の作成した「死亡診断書」もしくは「死体検案書」を添付する必要があります。
死亡届は再発行ができない書類なので、死亡届を提出する前にコピーを取っておくことをお勧めします。
2お金関係
(1)公的年金・健康保険の手続
国民年金の場合は亡くなった日から14日以内、厚生年金の場合は亡くなった日から10日以内に、年金事務所で年金受給停止の手続きを行う必要があります。
健康保険については、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入していた方は、亡くなった日から14日以内に市区町村に保険証を返納します。故人が会社の健康保険に加入していた場合は、手続き方法を勤務先に確認しましょう。
(2)死亡保険金の請求手続
故人が生命保険に加入していたら、死亡保険金の受取が発生するため、保険会社へ連絡をする必要があります。
連絡をする際は、証券番号が分かるもの(保険証券等)が必要です。
(3)公共料金等の引き落とし口座の変更
故人の口座は入出金ができないよう凍結されますので、公共料金等の引落とし口座の変更が必要です。
電気、ガス、水道、インターネット、携帯電話等、各種契約の契約変更や解約手続きを行うため、各契約先に連絡をする必要があります。
また、パスポートや運転免許証の返納も忘れずに行いましょう。
3相続人の調査
金融機関や不動産の登記等、相続手続きには、相続人であることを確定、証明するために、戸籍謄本が必要になります。
相続人の調査には、
・故人の出生~死亡まで連続した戸籍謄本
・故人に子がいない場合は、故人の両親の出生~死亡まで連続した戸籍謄本
・故人の両親も他界している場合には、故人の兄弟の戸籍謄本
・故人の兄弟も他界している場合には、兄弟の子(故人の甥、姪)の現在戸籍の謄本
・相続人全員の現在戸籍の謄本
と、故人に対する続柄により、様々な戸籍が必要になります。
戸籍は本籍地の役所で発行できます。
結婚や離婚、転籍、分籍、養子縁組など、戸籍の変動の多い方だと、取得に大変な時間を要す場合があるので、早めに着手された方がよいでしょう。
遠方の役所に依頼しなければならない場合は、郵送にて請求する方法もあります。
また、本籍地が不明である場合は、まず故人の住民票の除票を取得し、本籍地の確認を行いましょう。
この段階で、思ったよりも難しく、ご相談に来られる方が多いように思います。
電子化される前の手書きの戸籍の判読は、慣れていないと難しい上に時間もかかりますので、専門家に依頼されるのも1つの手です。
4遺言書の有無の確認
故人は遺言書を残していますか?
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」、という3つの種類があります。
(1)自筆証書遺言
遺言者自身が自筆で作成した遺言書のことを言います。
遺言者が亡くなられたときは、遺言を執行する(遺言書通りに相続手続きをする)前に、家庭裁判所にて検認の手続きをする必要があります。
こちらは故人が自ら作成・保管しておくものなので、遺品整理等の際に探さなくてはなりません。
(作成には費用も掛からず、遺言内容を死ぬまで秘密にできますが、家族に見つけてもらえなかったり、本物か証明できない場合や、正確に書かれていない場合(故人の手書きであることや、加筆・訂正等の方法等、細かなルールが決められています)、遺言書が無効になるデメリットがあります。)
(2)公正証書遺言
遺言者が、公証役場で公証人に作成してもらった遺言書のことをいいます。
作成には費用がかかりますし、作成時に証人に立ち会ってもらう必要があるため遺言内容を秘密にすることはできませんが、家庭裁判所での検認も不要であり、法的に有効な遺言を確実に残すことができる方法であると言えます。
こちらは、全国の公証役場にて遺言検索を行うことで、有無を確認することができます。
1.死亡の除籍謄本(原本)
2.被相続人と相続人の関係証明ができる戸籍(原本)
3.認め印
4.本人確認書類(免許証等)
が基本的な持ち物ですが、公証役場に出向く前に、必要な書類を確認してから行きましょう。
公証人や役場によって、印鑑証明書などを求められる場合もあります。
委任状(実印での押印)、印鑑証明書を提出すれば、代理人が手続を行うことも可能です(代理人が行う場合は、代理人の認め印、本人確認書類が必要です)。
(3)秘密証書遺言
故人が遺言書を作成して封入及び封印し、公証役場で証明してもらう方法で作成する遺言書のことを言います。
こちらも、自筆証書遺言と同じく、故人が保管しておくものなので、遺品整理等の際に探さなくてはなりませんし、遺言の執行前には家庭裁判所での検認が必要です。
(遺言書が本物であることを証明できるうえに、遺言内容を秘密にできる方法ではありますが、作成には費用が掛かる上に、こちらも家族に見つけてもらえない場合や、正しい書き方をしていない場合に、無効になってしまう可能性があります。)
なお、遺言書について、弊所のHPにて何度かご紹介しておりますので、よろしければご覧ください。(https://takiilaw.com/category/%e7%9b%b8%e7%b6%9a/%e9%81%ba%e8%a8%80/)
5相続財産の把握
次に、相続財産の把握をしなくてはなりません。
故人の家の中を整理する際に、通帳や保険会社からの手紙、証券会社からの運用報告書などから、相続財産を特定していく必要があります。
銀行の口座が分かっている場合は、死亡時点の残高証明書を取得しておくと、その後の遺産分割の際に、手続がスムーズに行えるかと思います。
また、不動産がある場合は権利証を確認したり、市役所にて固定資産税評価証明書を取得するなどして、建物や土地を特定しておく必要があります。
ここで、相続財産の把握に漏れがあると、相続税の申告や遺産分割協議についても影響する恐れがあるため、家の中をしっかりと確認しましょう。
また、相続財産の把握についてご不安であれば、弊所にて遺産調査も行っています。
お心当たりのある銀行にて口座の全店照会を行ったり、故人名義の不動産があると思われる市町村を教えていただければ、名寄せの手続を代理して行います。
6相続するか、放棄するかを選択する
財産とは、なにもプラスのものばかりが残っているとは限りません。
例えば故人に借金がある場合、相続すると、相続人で返済していかなければならないのです。
(1)相続放棄
故人にマイナスの財産が多大にある場合や、プラスの財産があっても相続したくないと思う時は、故人の死亡を知ってから3か月以内であれば、相続放棄https://takiilaw.com/category/%e7%9b%b8%e7%b6%9a/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e6%94%be%e6%a3%84/
をすることができます。
相続放棄を行うと、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がず、始めから相続人とならなかったものとみなされ、他の相続人で相続財産を分けることとなります(民法第938条)。
(2)限定承認
マイナスの財産もプラスの財産も、その総額が不明である場合に、相続人が相続によって得たプラスの財産の限度で被相続人のマイナスの財産の負担を引き継ぐ方法です。
ちょっとややこしい書き方になってしまいましたが、要は、相続人が相続財産から故人のマイナスの財産(借金など)を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法です。
相続人全員が家庭裁判所に、故人の死亡を知ってから3か月以内に申述する必要がありますし、みなし譲渡所得税という税金がかかる場合があります(不動産や株式等の財産がある場合)。
不動産等売却可能な財産があると競売をしなければいけない、申述後に公告・弁済を行わなければならない、準確定申告が必要であること等、とにかく手続きが複雑で、申述をしてから手続きが終わるまでに1年から2年かかることもあるようです。
例えば、故人が事業を行っており、後から誰かの連帯保証人になっていたために多額の借金の請求が来ることが予想される場合や、相続をしたマイナスの財産がプラスの財産より多いけれど、どうしても残したい実家のような不動産がある場合に行われるようですが、申述後の手続きが非常に複雑であるため、ほとんど利用されていないのが現状です。
(3)単純承認
相続人が故人の財産を全て引き継ぐことを言います。
故人の死亡を知ってから3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きを行わなかった場合、単純承認したものとみなされます。
また、熟慮期間(相続開始を知った時から原則3か月以内)に相続人が相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合や、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに、相続人が当然に相続を単純承認(被相続人の権利義務を無制限かつ無条件に承継)したものとみなされる制度(民法第921条)もあるので、借金などのマイナスの財産がある場合は注意が必要です。法定単純承認といいます。
なお、故人の死亡を知ってから3か月以内、というのが相続放棄や限定承認の期限となりますが、相続人の特定や財産の調査に3か月以上時間がかかってしまう場合、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間伸長」の申立を行うことで、その期間を延ばすことができます。
7故人の所得税の申告・納付(準確定申告)
故人に事業所得や不動産所得がある場合は、相続開始を知った日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。
故人が生前、毎年確定申告をしていた場合は、その必要があるかもしれないので、税務署や、故人が依頼していた税理士事務所へ確認をしてみましょう。
8遺産分割協議
相続人の把握と相続財産の調査が終ったら、遺言書がない場合、遺産分割協議を行います。誰がどの財産をどのように相続するかを、相続人全員で話合います。
ここで揉めてしまって、弁護士が登場するのが、ドラマや映画でよくある流れなのではないでしょうか。親族であっても、お金の話はみんなが敏感になるものです。
また、“遺言書がない場合”とさせていただきましたが、遺言書があっても、その内容に納得できない場合や遺留分(相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産)の請求について、ご相談いただくこともよくあります。
少しでも納得できない内容である場合や、遺言書に不審な点がある場合、すぐに弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。
9遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。
預金口座の解約や不動産の登記の際には、この遺産分割協議書が必要になります。
相続人全員で署名・押印する必要がありますし、手続きの際に遺産分割協議書と合わせて、相続人全員の印鑑証明書の添付を求められる場合もあるので、実印で押印されることをお勧めします。
また、記載に記入漏れや誤りがある場合、再度作成が必要になる場合があるので、間違いがないように注意してください。
今後、相続手続きをする先(銀行等金融機関や、法務局など)に、事前に記載方法を確認しておくのもいいかもしれません。
なお、相続人の中に未成年者がおり、その親もともに相続人となる場合、家庭裁判所に申立を行い、特別代理人を選任する必要があります。
通常、未成年者が法律に基づく契約などをするときは、親権者が代理人となります。
しかし、親権者と未成年者がともに法定相続人である場合はそうはいきません。
親権者が、自分の利益のために未成年者からすると不利益となる協議にしてしまうことがある(「利益相反行為」といいます。)ため、未成年者に「特別代理人」を立て、不利益を被ることのないように遺産分割協議を行います。
特別代理人は相続の当事者でない成人であれば誰でもなることができますが、相続の内容や家庭の事情を知られるため、親族に依頼する方が多い印象です。
ただし、特別代理人の候補として届出た人が適任でないと判断された場合、家庭裁判所によって弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。
10遺産分割協議書が完成したら
遺産分割協議書が完成したら、それを用いて銀行口座や有価証券等の解約、名義変更や、不動産の相続登記を行います。
11相続税申告書の作成、申告、納付
相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告、納付の手続が必要になります。
相続開始(死亡を知った時)から10か月以内に行わなければいけないため、ここまでの手続について、早い段階から準備しておくとよいかと思います。
12まとめ
いかがでしょうか?
以上が、相続に関する基本的な流れになります。
思った以上にやることがあるため、驚かれた方もいるのではないでしょうか。
相続手続きは、そう何度も身に降りかかることではありません。
限られた時間の中で、慣れない手続を行い、他の相続人と話合い、話をまとめるのは本当に大変かと思います。
そんなときのために、我々専門家がおりますので、お困りの際はいつでもご連絡ください。